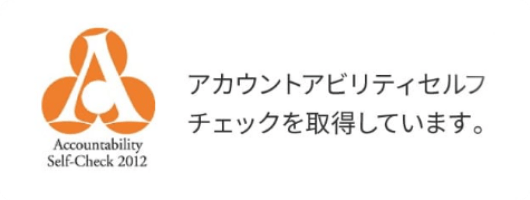JP EN
BAJについてAbout us

目指す社会・理念・使命
VISION
目指す社会
信頼と活力をはぐくみ、
分かちあうアジア
地域の住民と一緒に考え、行動し、住民の自立を図ることで、
アジアの人々がお互いに助け合える社会を目指しています。
PHILOSOPHY
理念
違いを超えて、
知恵を出し合い、
ともに生きる道を探る
貧困、難民、環境破壊など、国境を越えた世界規模の問題に直面する現在だからこそ、
地域から考え、地域で行動を始めることで、解決の道を探ります。
特に日本と関係の深いアジアの人々と連帯し、政治体制や宗教、民族言語、文化の違いを越えて、
相互理解の架け橋となれるように活動に取り組みます。
MISSION
4つの使命
アジアの人々がお互いに助け合える社会を目指して、BAJが相互理解の架け橋となれるよう、
4つの使命を定めています。
1 技術習得や能力強化の機会を
提供します。
2 収入向上を支援します。
3 地域発展のための環境基盤を
整備します。
4 環境を守り啓発を進めます。
活動紹介
BAJは「違いを超えて、知恵を出し合い、ともに生きる道を探る」という理念のもと、
困ったときはお互い様のアジアを目指し、ミャンマー・ベトナム・日本において
4つの使命に紐づく事業をおこなっています。
-
人づくり
技術習得や能力強化


-
基盤づくり
環境基盤整備


-
雇用づくり
収入向上


-
社会づくり
啓発活動



同じアジアに生きる仲間として、
違いを超えて助け合えるアジアを
ともにつくりませんか?
Copyright(C)2024 BRIDGE ASIA JAPAN. All Rights Reserved.